シリーズ・放送人インタビュー2011 <第18回>神津友好氏
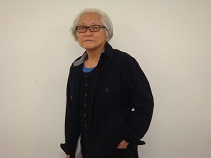
神津氏は1925年、長野県に生まれた。1947年に上智大学、1950年に法政大学を卒業し、放送演芸作家として活躍している。代表的な著書には、『笑伝 林家三平』、『少年少女名作落語』などがある。 「私達の時にはちょうど例の、太平洋戦争というものが、第2次世界大戦が差し掛かっているんです。ちょうどその学生の時期に。戦争に、学徒出陣と呼ばれた兵役に1年行ってるんです。」 神津氏は上智大学の新聞学科であった学生時代の昭和19年に国から召集命令が下された。幹部候補生として日本で育成を受けつつ、新聞学科生として新聞報道にも携わった。そして、国内での訓練中、昭和20年に終戦を迎えたのである。 「終戦後の昭和24、5年なんてのはどんな時代かというと、正直僕らみたいないい加減なものを書いても持ち込めば売れるんです。いい時代でしたね。ろくなもんじゃありませんでしたよ。それは」 上智大学を卒業後、より文学上の知識を得るため、昭和21年に法政大学文学部に入学し、学生の頃から本を書いて名作ものの翻訳など二、三の出版社から出すことができた。そして、落語・漫才を中心とした作家活動をこなすようになった。演芸作家は落語、漫才、漫談、浪曲、講談それぞれを書けることが第一条件である。しかし、現代ではそのような演芸作家に相応しい作家が少ない。そこで教室などを開いて演芸作家を目指す人々を育成することにも力を入れている。しかし、演芸作家として活躍することは本当に難しいことである。 「一発書いて売れるってもんじゃないんでね、そんな苦しい訳ですよ、演芸の世界ってのはね。一発でネタが尽きちゃう人もいる訳だ(笑)。そういう実は厳しい世界なんですね」 また、お客さんとの共感が大切なことであり、その場の演者と観客の一体感を味わえるという点が演芸作家のおもしろさ、そしてやりがいである。 「涙が出るほど嬉しいのはね、自分が書いて仕掛けようと思ったものがね、明らかにお客様の共感の中で拍手がくるとか、どっと笑ってくれることね。これ以上の楽しみはありません」 演芸作家に求められるものは、人に笑われるのではなく、笑わせる作品を作ることであり、社会や人々の人生に何らかの影響を与えられるものを一筋に作りだすことである、と神津氏は語った。 インタビュワー主担当:金澤智 副担当:徳岡礼菜