シリーズ・経済ジャーナリストインタビュー2015 <第18回>島田昌幸氏
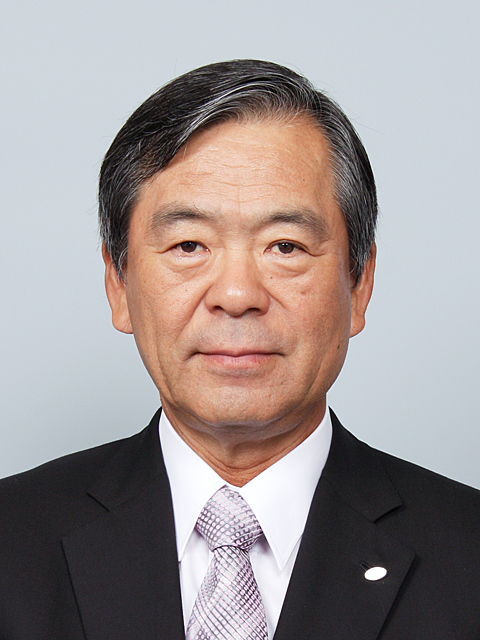
島田昌幸氏は1945年東京に生まれ、1965年に早稲田大学政治経済学部政治学科に入学した。 ジャーナリズム研究会に入り、60年安保時の七社共同宣言を知り学費学館闘争を経験して、ジャーナリストになろうと決意。 1969年に日本経済新聞社に入社した。 大阪の社会部に配属され、四年を過ごしたのち、大阪の経済部へ異動となり繊維業界を担当、 綿紡績三社の業務提携を特ダネで書き、大阪で初めての編集局長賞を取る。 また、1973年に創刊したばかりの『日経産業新聞』にも多くの記事を書いた。 他に、本紙夕刊掲載のさまざまな業界人へのインタビュー記事にも苦闘した。 社会部と経済部合わせて16年所属した大阪を離れ、1985年に東京の産業部へ異動。 二年後の1987年に東京経済部のデスクとなった。 「東京の経済部はマクロ経済と金融が中心になっている所なんです。…官庁や日銀を取材する所でしたから、僕にとっては全く異質な世界でした。 大阪の経済部というのは、…ほとんどが産業ミクロの取材だったから、…そういう所にデスクとして行っても、出先の記者には馬鹿にされるし、 むちゃくちゃな人事だと思ったけれど仕方ないから、体力で頑張るしかないと…「一番会社に長くいるデスク」という異名までもらった」と語った。 1991年に九州の西部支社編集部長に就任し、1992年の雲仙普賢岳噴火の取材の混乱の中、 東京から派遣されてきたカメラマンを亡くしてしまう。 その事故死をきっかけに「どんなやり方でも良いから報道しろ、世界中の人に発信しろ、だけど絶対に自分の身に危険が及ばないようにしろ、 これがなかなか上手く両立するかどうか」という問題を長く抱えることとなった。 2000年に社長室長となり、経営陣に加わってから、 イトマン事件やTCワークスの架空請求事件など『日経』に関わる数々の事件に直接巻き込まれた。 株主代表訴訟やモデル小説訴訟を経て、2005年にテレビ東京の専務取締役となる。 テレビと新聞の違いについて島田氏は「新聞というのは原則、一人の記者が取材して原稿を書き、 …全国の販売店の人が配って、後に行くほど人が沢山かかる。テレビは作る時に色んな人が参加する。 …送る時はボタン一つ。作るまでに沢山の人の手がかかる」と「製作形態と伝達形態」の観点から構造が逆であると分析する。 また、『日経新聞』については、「経済を中心としながら、様々な情報、文化や芸術を含めて、日本のクオリティペーパーを目指そうとした」と述べ、 その信頼性の向上を高く評価した。 インタビュワー主担当:則常麻里子、副担当:藤原拓也