シリーズ・海外特派員ジャーナリストインタビュー2014 <第16回>長賀一哉氏
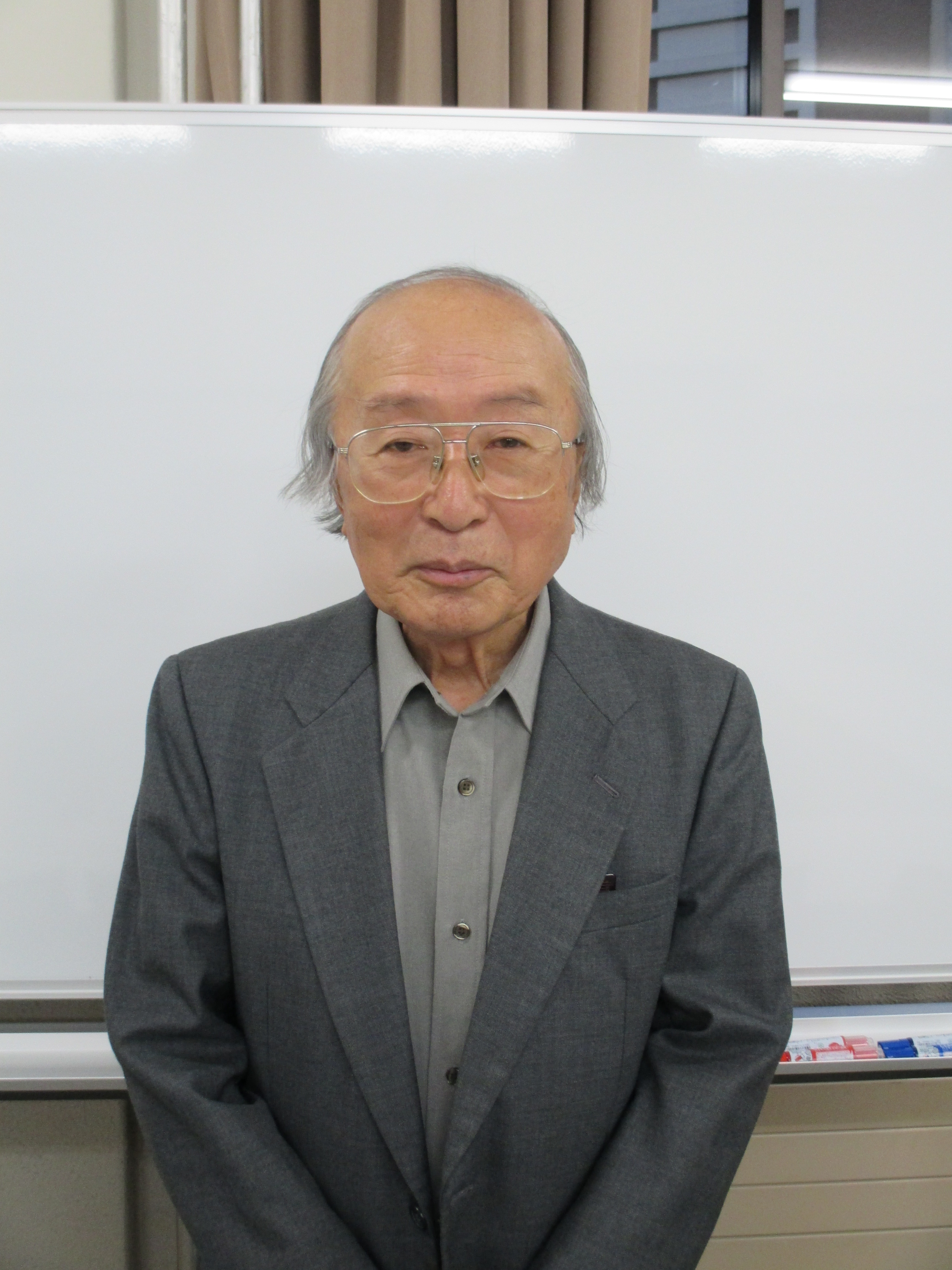
長賀一哉氏は、1937年新潟県に生まれた。1957年に東京大学文科二類に入学し、文学部西洋史学科に進んだ。学生時代は音感合唱研究会に所属。安保闘争の中、「このままじっとはしてられない」と学生運動にも参加、ロシアに関心を抱き、スターリンの「一国社会主義」をテーマに卒論を執筆。学生運動に明け暮れ「これ(記者)しかどうも飯食う所はなさそうだ」と、1961年に共同通信社に入社。 札幌支局、旭川支局配属時には、北大スラブ研究室に出入・オた。旭川支局長の推薦で、1964年に本社政治部。佐藤番と公務員制度審議会の取材を掛け持った。1967年に外信部に異動した。当時の外信部は「自由闊達で…物事を話すことが比較的自由で、あまり上の人を気にしないでやれる」雰囲気だったという。1969年にはサイゴン特派員として、「解放戦線」を取材した。1971年サイゴン支局長となるが、国外退去を命じられる。「『どうして、何でですか』と言っても理由を教えてくれない。」その頃から戦火はインドシナ全体に広がり、1973年には情勢を「自分の眼でもみたい」と一ヶ月にわたりプノンペンとバンコクに出張。 1974年にワシントン特派員になり、ラロック証言とロッキード事件を取材する。1981年にはモスクワ支局長となるが、外国人記者は隔離され、政府から派遣された助手に監視されている状態で、取材はろくにできず、「仕方がないのでタス通信を見た」と言う。1987年経済通信局編集部長、1989年情報統括本部部長、1992年に論説・編集委員となり、モスクワ・キエフなど東欧九ヶ国に出張し、「変わる国、変わる人」を執筆。1997年に論説副委員長となり、同年定年退社。2002年まで北九州市立大学外国語学部国際関係学科教授。 海外特派員が取り組むべきことは「自分が関心を持った国の言葉を勉強」することで、それにより、「相手の人と話す時の気持ちも変わる」と言う。また、「今はイデオロギーが崩壊したような時代だから、全体を見回して…何が大事で何が大事でないか、判断」する必要性を説く。外信部記者にとっては「色づけしないで、聞いたことをそのまんま出すこと」が大切であると述べ、日韓・日中関係が冷え切る中、日本のメディアは「両方の立場をきちんと伝え」る報道をすべきだと語った。 インタビュワー主担当:木下将太郎、副担当:尾崎彩